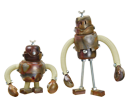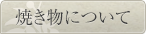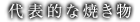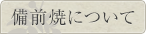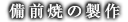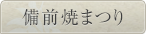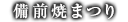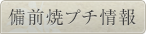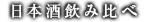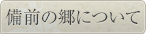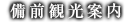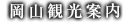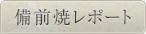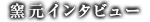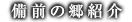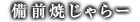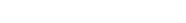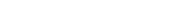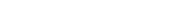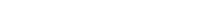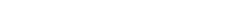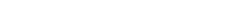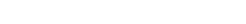備前焼は釉薬を使いませんが、焼きあがった作品にはさまざまな色や模様がついています。
これは、長時間じっくり焼き締めている間に、粘土に含まれる金属成分が変化したり、窯の中の温度や松割木の灰、窯入れの際に入れた藁などが、作品と重なりあって現れるのです。作家の経験と計算に偶然がプラスされてできる焼き色は、この上なく神秘的で備前焼の美しさの根源でもあります。
胡麻のような粒がついているのが特徴です。
焼成中に松割木の灰が火勢によりふきつけられ、その灰が高い熱により釉化(ガラス化)してできます。
灰が多く降りかかり、溶けてバナーのようになったものや、灰が溶けて垂れ流れているもの(玉垂れ(たまだれ)や流れ胡麻と呼ばれます)もあります。
色は、白や黄、青などさまざまです。

黒色から灰青色などの色の変化が模様になっているのが桟切です。
燃料が燃え尽きてできた灰に作品の一部が覆われ、空気の流通が悪く還元焼成(いぶし焼き)になった部分に色の変化が現れます。
炎があたる部分は、赤褐色、灰で覆われた部分は黒く、その境目は灰青色になるのが一般的です。
昔は、窯の内部を桟(さん)で仕切っており、この桟の下で焼かれる作品にこの模様が現れたので桟切(さんぎり)と呼ばれるようになりました。

火襷(緋襷)は、うす茶色の素地に、赤、茶、朱色などの線が「たすき」のようにかかった模様です。
素地に藁を巻いて、作品を「サヤ(陶器を焼くための容器)」に入れて焼くと、炎や灰が直接あたらないため、作品全体は素地に近いうす茶色に焼け、藁があたった箇所は、緋色に発色します。
火襷の模様は、藁のカリウムなどの成分と、素地の鉄分などの化学作用によるものです。
本来は、作品を重ねて窯詰めをする際に、作品同士ががくっつかないようにするために藁を巻いていました。これが模様として用いられるようになりました。

赤や茶色のぼた餅のような丸い模様が牡丹餅です。
牡丹餅は、作品の上に、丸めた土や小さい作品を置いてできた焼けむらが模様として美しく発色したものです。
まるでぼた餅を並べたような模様に焼きあがることから牡丹餅と名づけられました。
この模様も、火襷と同様、窯詰めの際に、器同士を重ねるための緩衝材的役割で使われていたものです。

窯の中の酸素があたらない場所で焼かれると、物質から酸素が奪われる反応(還元)がおきます。この強還元状態で焼かれた作品は、鮮やかな青灰色に発色します。
酸素がなければないほど、水色に近い青になります。
この青備前は、必ず意図したとおりの発色になるとは限らず、また、釜の中でも還元状態になる場所が少なく、生産が非常に困難なことから、大変珍重されてきました。

伊部手(いんべて)と呼ばれる技法により、成形後に鉄分を多く含んだ土を表面に塗り焼き上げることで、表面の土が早く溶け出し釉薬のような働きをするため、他の窯変とは少し違った質感になります。鉄分の量により焼き上がり色の濃さに違いがあり、紫蘇色から黒の発色があります。
また、鉄分の多い粘土で成形するなど、その製法は作家により異なりますが、いずれも独特の風合いになります。
古くは18世紀初頭に、白い土に白や透明の釉薬を使用して高火度での焼成にて作られていたようですが、後に、鉄分の少ない土を焼しめることにより、釉薬を使用せずに白を出せるようになりました。
あまり作られない時期があったことや、製法が作家により異なることなどから、非常に希少であり、古いものは骨董品としても重宝されています。